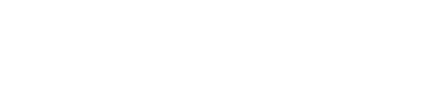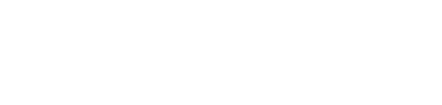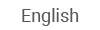研究内容
小さな精子核に秘められた大きな謎を解明する
DNAの塩基配列変化を伴わずに遺伝子発現や細胞表現型の変化をもたらす転写調節機構を「エピジェネティクス(epigenetics)」と呼びますが、多細胞生物では細胞の運命決定に重要な役割を果たします。つまり個体が発生する過程において、全ての細胞がそれぞれの細胞種に特異的なエピジェネティクス制御を受けながら増殖・分化を繰り返すことで、全ての組織が形態的・機能的に成熟します。
哺乳動物の雄性生殖細胞は生後、始原生殖細胞から分化した前精原細胞の一部が組織幹細胞である精子幹細胞となります。精子幹細胞は非対称分裂によって幹細胞を維持し続けるのと同時に、娘細胞である分化型精原細胞を産生します。後者は一定回数分裂したあと減数分裂期に入り、四倍体である精母細胞を経て、減数分裂終了後には一倍体細胞である精子細胞となります。精子細胞はさらに頭部(核)が小さく凝縮し、尾部の伸長を進めながら分化して精子となり、最終的には精巣上体に泳出されて妊孕性を獲得します。この一連の精子形成過程において、雄性生殖細胞は形態学的にも機能的にも劇的な変化を遂げますが、この大きな変化を支える主要な分子基盤がエピジェネティクスです。
岡田研究室の目的は、この雄性生殖細胞の増殖分化に関わるエピジェネティックダイナミクスを明らかにすることです。現在は生殖細胞の分化段階に応じて、次のようなテーマ・アプローチで研究に取り組んでいます。
2025年度版
精子クロマチン構造と経世代効果、臨床的応用に向けた研究
減数分裂期を終えた雄性生殖細胞は一倍体細胞となり、精子形成に向けて更なる分化を開始します。このときヒストンの大部分(90%以上)はクロマチンから脱落し、代わりにプロタミンと呼ばれる小型塩基性蛋白質がクロマチンを置換します。これによって精子クロマチンは高度に凝縮し、精子は妊孕性を獲得しますが、ごくわずかに残存するヒストンの生理学的意義は長年明らかにされていません。近年、雄個体が受けた様々なストレスが精子のエピジェネティクス変化を起こし、さらに次世代に受け継がれる、いわゆるエピジェネティクスの経世代効果が様々な動物種で報告されています。このことから、このわずかに残存するヒストンの正確なプロファイリングやゲノム局在の同定、経世代効果を明らかにすることは分野内における重要な課題です。
当研究室では精子残存ヒストンのバリアントや修飾形態を網羅的に探索し、生殖細胞特異的H2AバリアントTH2Aにおける新規のリン酸化修飾を見出しました(図1)。またこのリン酸化修飾はHaspinと呼ばれるリン酸化酵素で触媒されること、さらに減数分裂中期(metaphase)や精子核凝縮などの染色体凝縮時にのみ特異的に起こることを見出しました。この現象は卵子でも共通しており、さらに卵子におけるTH2Aリン酸化修飾の程度は、マウス個体の加齢によって著しく減弱することを見出しました(図2)。つまり、TH2Aのリン酸化修飾は、新規の染色体凝縮マーカーであるのみならず、卵子の加齢マーカーとしても有用であることを示しました(Hada, Sci Rep., 2017; Hada, Chromosoma, 2017)。

TH2Aのリン酸化修飾は核凝集した精子細胞に存在する。緑色はTH2Aのリン酸化修飾、赤色は精子細胞のアクロソーム、青色はDNAを示す。白い破線は精細管の辺縁部、ローマ数字は精細管の分化段階を示す。(Hada, Sci Rep., 2017)

第一減数分裂中期のマウス卵母細胞において、TH2Aのリン酸化修飾はセントロメア領域に存在するが、老化卵においてはそのシグナルが減少する。緑色はTH2Aのリン酸化修飾、青色はDNAを示す。白い矢印は拡大部分を示す。(Hada, Chromosoma, 2017)
さらにこのTH2Aを含む精子残存ヒストンの局在を、精子クロマチンに最適化した改変クロマチン可溶化方法の開発と並行して検討しました。その結果、精子残存ヒストンの大半は非遺伝子領域に局在する一方で、メチル化修飾を受けたヒストンはその修飾に依存して特徴的なゲノムエレメント上に残存することがわかりました(Yamaguchi, Cell Rep., 2018)(図3)。この残存パターンは雄マウス個体の加齢によって変化することを見出し、現在その経世代効果を検討中です。さらに精子ヒストンの除去に、ヒストンのユビキチン化が関与することを、ノックアウトマウスの表現型解析を通じて明らかにしました(Kim, Cell Rep., 2020)。

このような精子クロマチン研究は専らマウスを用いて実施してきましたが、「不妊治療大国」とも呼ばれる日本のニーズの高まりを鑑み、生殖補助医療クリニックと連携してヒト精子を用いた研究を開始しました。DNAの損傷は精子の臨床検査項目のひとつとして普及しつつありますが、DNA損傷の原因ともなり得るクロマチンに関する検査項目は多くありません。また上述のように、エピジェネティクス研究分野では近年、エピジェネティクス情報の経世代遺伝現象が大きな注目を集めています。これらの事実を考慮すると、精子エピジェネティクスのクオリティチェック方法の確立は重要な課題です。現在は次世代シーケンス技術を用いてヒト精子クロマチンの定量を試みると共に、医療機関と提携して診断に有用な精子染色試薬の開発などを進めています。
減数分裂期の軸構造形成に関わる因子の同定と機能解析
減数分裂は、父方由来と母方由来の染色体が遺伝情報の部分的な交換を行うことで、次世代に遺伝的多様性を与える役割を担っています。第一減数分裂前期は、DNA二本鎖切断、相同組換え、相同染色体の対合、交差、分裂等の分子イベントを経ながら進行しますが、これら一連の過程の多くが染色体軸上で行われています。染色体軸は哺乳類の場合、コヒーシンとシナプトネマ複合体とよばれる二種類の因子によって構成されています。この軸構造は、減数分裂の開始とともに形成され始め、そこにHORMADタンパク質(HORMAD1、HORMAD2)などが局在することで各イベントに必要な因子を軸上に呼び寄せます。さらに、HORMADタンパク質は対合の起きていない染色体軸に沿って局在し、ホモログシナプシスを監視することが知られています。しかし、決定的なDNA結合ドメインを含まないHORMAD タンパク質が、染色体軸に局在する分子メカニズムはこれまで不明でありました。本研究では、HORMAD1の染色体軸への局在メカニズムおよび減数分裂特異的コヒーシンである RAD21L/REC8との相互作用の解明を試みました。その結果、第一減数分裂前期の軸形成初期において、HORMAD1は、RAD21LおよびREC8とごく近接して局在していました(図4)。そして、各因子のKOマウスを用いた解析から、HORMAD1のクロマチン上の局在は、軸形成前にコヒーシンによって媒介され、このHORMAD1とコヒーシンとの相互作用はSYCP2によって部分的にサポートされている事が明らかとなりました。さらに、その後の軸形成過程においても、HORMAD1は RAD21LおよびREC8と部分的に近接した局在パターンを示し、協調する事で軸形成に寄与している事を明らかにしました。(Fujiwara, PLoS Genetics, 2020)

HORMAD1(緑)とRAD21L(マゼンタ)を免疫染色により蛍光標識し、超解像顕微鏡を用いて撮影した。